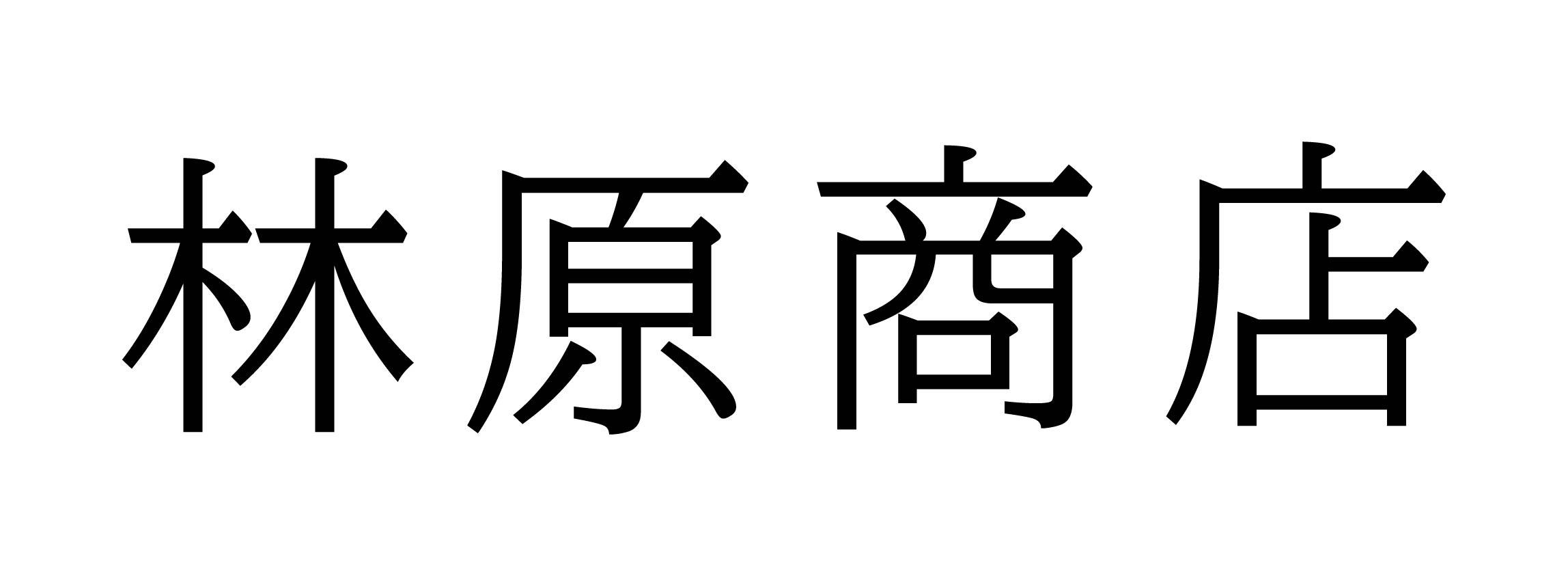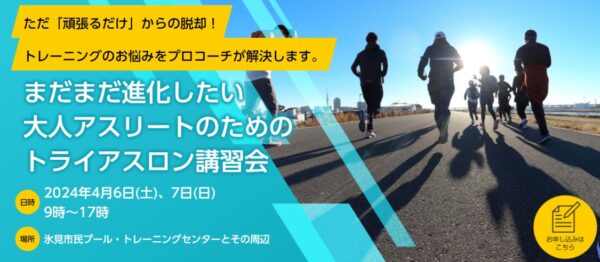春のロングライド
2023年9月3日(日)に新潟県佐渡市で開催された佐渡国際トライアスロン大会のAタイプ(スイム 4.0km、バイク 190km、ラン 42.2km)を完走し、アストロマンになりました! 「ガンガン練習しているイメージもないのに、そんな大会を完走したとは…!?」という驚きのお声もいただいたため、今回は大会にむけた経緯や戦略、練習内容も含めてご紹介。「林原ができるなら、自分もできそう!」と思っていただけると幸いです。

目標を明確にして行動に落とし込む
トライアスロンに限らず、目標を達成するには、方法があります。達成するまでに適切な行動をとることです。
私が以前から取り組んでいる「コーチング」は、目標を明確化して、そこまでの行動を考えて実践していくことにも役立ちます。

普段はビジネスやブランディングのコンサルティングや取材時に活用しているスキルですが、今回の目標「佐渡国際トライアスロンを完走する」にももちろん応用できます。
情報を集める
「彼(かれ)を知り 己を知れば 百戦殆(あや)うからず」という孫子の有名な一説があります。
「敵と味方の実情を熟知していれば、百回戦っても負けることはない」という意味です。
またこのあとには、以下のように続きます。
「彼を知らずして己を知れば、一勝一負す。彼を知らず己を知らざれば、戦う毎に必ず殆し」
「敵情を知らないで味方のことだけを知っているのでは、勝ったり負けたりして勝負がつかず、敵のことも味方のことも知らなければ必ず負ける」ということです。
これは現代にも、トライアスロンにも、通じる真理です。
叶えたい目標があるなら、その目標を達成するために必要なこと(時間・お金・人材・スキルなど)と、自分の力量をよく知る必要があります。
今回は、佐渡のコースの特徴や制限時間・関門、エイドの場所や支給物の情報などをまず把握すること、自分の力量を正確に知る必要がありますね。
3C分析で状況を認識
「3C分析」とは、マーケティングの分析に使われる考え方のフレームワーク(枠組み)です。
Company(自社)、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)という3つの「C」について分析することで、事業計画やマーケティング戦略を立案するときに用います。
私はブランディング戦略立案やコンセプトをづくりのお手伝いや、コピーライティングのヒアリングなどに、この3C分析を使います。
今回の場合、「自社」は自分の力量や長所・短所、「顧客」は「佐渡トラ」、「競合」は「他の選手」に読み替えてみましょう。
3C分析で見える課題
自社(自分)
自覚している長所と短所には以下のようなことがありました。
短所……心配機能・筋力・筋持久力など十分とは言えず、追い込みきかない(咳喘息の発作が出ます)。特にバイクが遅い。足に麻痺が少しあり、ランのスピードが出ない。練習時間が少ない。
長所…妊娠・出産を経て、「辛いこと」に耐えるメンタルは強め。スイムはゆっくり力を抜いて泳ぐのが得意。「腰抜き」の追い越しができるなどわりと器用。ランは遅いけれど、歩かない粘りはある。暑さには強い。佐渡トラは3回目で慣れている。練習仲間がいる。家族が協力的。
こう見て見ると、先天的な身体能力や生活状況にはマイナス面が多いものの、プラス要素もいろいろありますね。
なお、正確な心肺機能を知るためには、循環器測定を受けるのがオススメです。私はこの測定を受けて、自分の乳酸性作業閾値(=LT)やそのときの速度やそのときの主観的な強度を確認しました。
ちなみに、私のLT閾値は、6分15秒/km~5分15秒/km。このときの心拍数は160拍/分前後です。つまり、5分15秒/km、心拍数160を超えると、まもなく潰れるということです。
また、最大酸素摂取量(=VO2max)は45ml/kg・分とアスリートなら高い数値とはいえず、追い込みが苦手であることがわかります。
1年前の佐渡トラBのタイムも確認しました。
スイム2.0km 0:44:10、バイク108.0km 4:32:49、ラン21.1km 2:41:17をAタイプの距離に置き換えてタイムを計算すると、スイム4.0kmが1時間30分、バイク190.0kmが8時間40分、ラン42.2kmが5時間30分くらい。
制限時間は、スイム2時間40分でクリア、バイクはスタート関門9時でランスタート関門16時30分で7時間30分だと、スイムの貯金があってもギリギリです。
ランはスタート関門にスタートすると5時間。30分足りません。
これはつまり、Aタイプ完走は、このままだと不可能です。特にバイクをもっと速くしないと、ランを走らせてすらもらえません。
また、ランも5時間ではこころもとない。※LT値はあくまでも計測上でバイク190kmの後に5分15秒/kmで42kmを走れる気はしません。6時間くらいみておきたいところです。
このままだと完走はかなり怪しいですよね。完走には、バイクの改善が必須です。
ただ、バイクさえ足きりに合わなければ、ラン後半のスピードが落ちなければ、目標達成の可能性がわずかかもしれないけれどある……ということでもあります。
顧客(佐渡トラ)
佐渡トラのコースやエイドの場所を確認したほか、競技説明会動画も何回も見ました。
バイクは190kmを8時間で走るとして時速約24キロ。坂や向かい風があることを考えると、私にとってはゆっくりとは言えないスピードです。
バイクの関門とエイドは表を作ってバイクにつけて、いつでも確認できるようにしました。
競合(他の選手)
他の選手の参戦記や練習内容をブログやSNSを通じて確認しました。
そうした情報を発信しているのは、男子・女子とも強い方ばかり。私はほかの選手に比較して、体力的にも練習内容にも劣ることがよくわかります。
私は「これは無理な目標だったかしら…」と弱気になりました。
そこで、「ギリギリ完走」した方のブログを探したところありました!

滋賀県でリハビリテーション医師をされているトライアスリートの方のブログです。
「佐渡Aギリギリ完走」を目標として計画・実践された記録が、お医者さまらしい科学的根拠やデータ分析とともに詳しく紹介されていました。
このブログのおかげで「私にも可能性は0ではないかも」と信じることができました。ありがとうございます!
「リハビリ先生(と勝手にお呼びしていました)」によると、「スイムは大差ないから泳ぎ切ればOK。バイクは26km/hでOK。バイクで8時間10分を超えると完走者がぐんと減る。ランは6時間残せば8分/kmでOK。ランが6時間あれば完走の可能性が高い。バイクで5時間30分を残せなければ、その人たちの完走率はわずか25%」とのことでした。
リハビリ先生でも、バイクは私よりずっと速い。バイクの改善がやはり何よりの課題であることを認識できました。
ゴールデンサークル理論
ゴールデンサークル理論とは、「WHY(なぜ・目的)」→「HOW(どうやって・方法)」→「WHAT(何を・具体的内容)」の順番で物事を考えるフレームワークです。
これは、事業計画や商品・サービスの企画、HPや書籍などの企画案づくり、プレゼン資料作成など、さまざまなことに使える考え方です。
今回の佐渡トラAギリギリ完走プロジェクトでは、以下のように具体的な行動目標へと落とし込みました。
「WHY(なぜ・目的)」
佐渡国際トライアスロンのタイプAを完走したい(ギリギリでもよい。というか、私にはギリギリでも難しい)
「HOW(どうやって・方針)」
3C分析の結果、分かったこと。
練習時間は増やせない。パワーを上げて、追い込んで、スピードアップするのは難しい。男性アスリート的選手や女子トップ選手の真似は、身体能力的にも時間的にもできない。バイクが遅すぎる。
弱者の戦略としては「遅くならない」「後半落とさない(ラクに進む・つぶれない)」に注力する。
「WHAT(何を・具体的方法)」
そして、方針が決まったら、実行可能な具体的な方法を考えます。以下は留意した主なことがらです。
スイム…速くなくていいので、とにかく完泳する。
そのために注力すること「ラクに泳げるフォームを追求」「バトルを避けるための『腰抜き』を完璧にする」「他者にくっつくコバンザメ泳ぎを上手くする」「水中でゴーグルを付け替えられるようになる」
バイク…少しでも抵抗を減らして速度を上げる。遅くならない。
そのために注力すること。「坂上りが効率よくできるフォームを身に着ける」「怖い下りでスピードを下げないよう、安全な乗り方を習う」……というわけで、アスロニアの志賀高原合宿に参加。
このほかにも「平地のスピードが上がるポジションを見つける」「風の抵抗を抑えるためDHポジションと下ハンドルで長く走れるようになる」 を目指して、近所の土手を行ったりきたり。
「ノンストップで走る距離を伸ばす(エイドで降りない)」「補給食を吐かないよう、ロングライドで食べる練習をする」などなど。
バイクは特に強化というか、楽化に努めました。
特に補給食については、グルメライドや気ままに休憩をとる長距離ライドは役に立ちません。
レースと同じように暑い時間にバイク上で補給食をとりながら100km以上走って、胃腸の具合を確かめました。
なお100kmすぎると嘔吐しやすく、すべてをパンなど固形食にすると脚が痙攣しやすくなることが分かり、100kmまでは固形食、それ以後はマグネシウムやクエン酸、塩分などを含むジェルをとることにしました。
ラン…ランスタート関門ギリギリスタートでも、7分/kmで間に合う
バイクの制限時間をクリアできれば、あとはフルマラソン(+5m)で残り5時間です。
7分/kmでフルマラソンは4時間55分22秒。フレッシュな足でマラソン単体を走るなら、私レベルでもクリア可能なタイムです。
ただし、佐渡トラはバイク190kmの後。疲労具合が読めません。
そこでやったことは「足腰に負担のかからず、疲れたときもラクに走れるフォームの追求(真下着地・重心の位置・背筋を伸ばすなど)」「ロングライドの後は、疲れた足でブリックランもする」「足にあったシューズに買い替える」など。
練習会で走るときも、疲れてからのイメージで、心拍数を上げ過ぎず、力ではなく、地面からの反発と体重移動で進むことを意識しました。
また全般的な留意点としては、以下のようなことを行いました。
・長時間動き続けることに慣れる(週末に100~150kmのライドや2部練) 仲間がいるってありがたいことですね。
・熱中症にならないよう、暑熱順化する(暑いところで短時間トレーニング)
・レース中にトイレに時間をとられると、ギリギリの民としては命取りです。納豆、ヨーグルト、キムチなどで腸内環境を整え、「朝のコーヒーのあとはトイレに行く」という習慣にして、条件反射で出やすい体質にしていきました。
・レース当日は朝2時半起きがつらくないよう、だんだんと朝方に生活時間をずらし、レースの週は3時起きで過ごしました。
現状把握と練習方針と具体的な行動目標が決まったら、次の問題はそれを「いつやるか」。
次回はスケジュールのお話を!
これでいいのか自信がない……迷ったときは「言語化コーチング」
自分ではうまく言えない、うまく書けない……そんなときは、林原商店の言語化コーチングがオススメです!
お話を伺いながら、漠然とした想いやうまく言えないお考えを質問で引き出し、整理することからスタート。
ビジョン・ミッション、コンセプトなどを自分らしい言葉にしたり、ビジネスプラン・商品・サービスの企画をお手伝い。
理想に向かうための言葉やコンテンツづくり、オウンドメディア(自社媒体)やSNSの運用についてもアドアイスさせていただきます。
また、コピーライティングや読み物記事、理念と独自性を伝えるHP制作などを、ワンストップでお引き受けすることも可能です。
お申し込みはご連絡フォームからどうぞ! 精一杯サポートさせていただきます!
お仕事のご依頼
メルマガ登録はこちらから
ここだけに掲載している林原りかの「自分史的自己紹介」をお届け後、言葉やブランディングで、ビジネスと人生を充実させるヒントをお伝えしています。返信もOK!