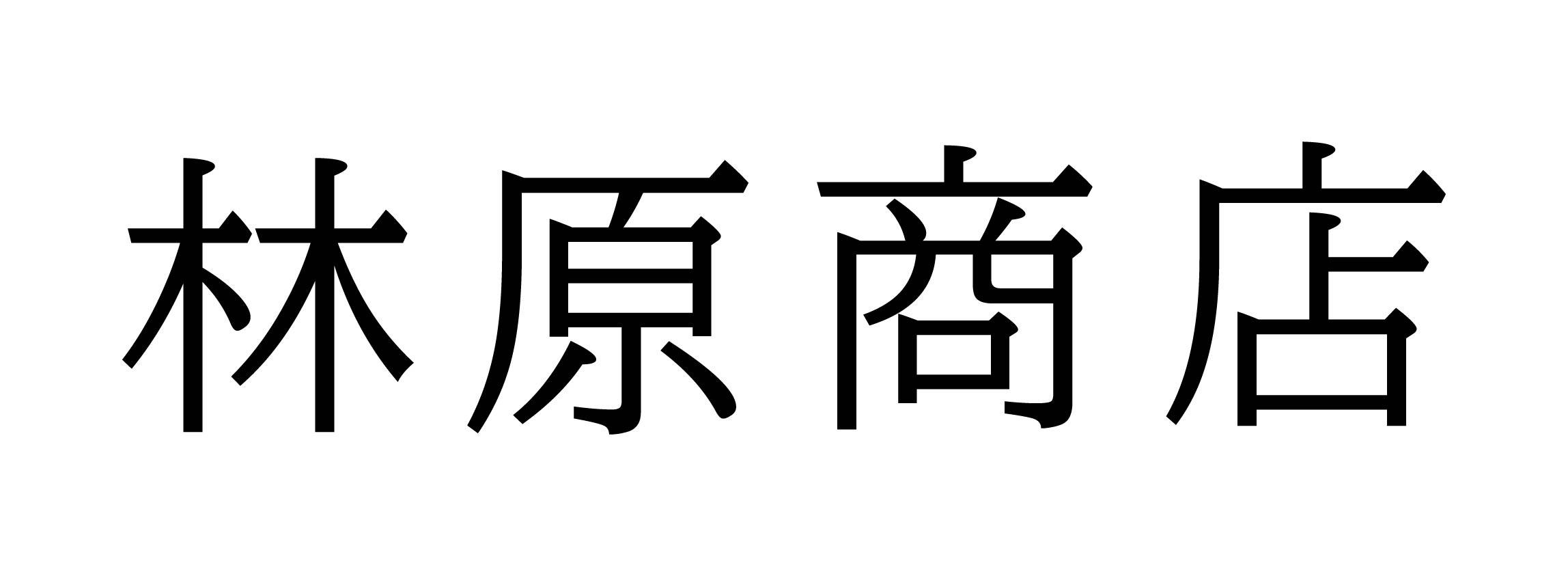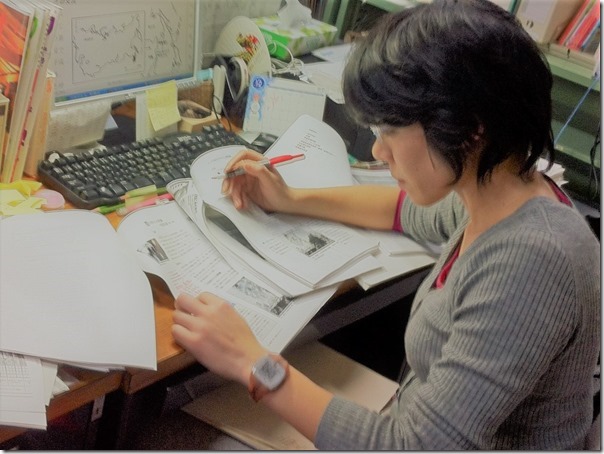記念誌・社史・家族史などの冊子をつくるとき、精度を上げるために欠かせない工程が「校正」です。複数の人でチェックすると煩雑になりがちな校正紙チェックのコツをご紹介します。
【編集者が校正することもよくあります(2011年12月16日撮影)】
校正の役割とそれぞれで見るところ
校正は、校正刷りと原稿を照合して、誤字脱字や表記の不統一、レイアウトの間違いなどを正す工程です。1回目を初校、2回目を再校,3回目を三校と呼びます。
編集を外注されると、統計を取ったわけではありませんが、校正は2回を標準としているところが多い印象です。
林原商店でも、よほどの事情がなければ、校正は2回でスケジュールを組んでいます。
初校を出す前にデザインはデザイン見本(組見本)で全体のテイストをあらかじめ確認しておきます。文章はWordなどで、大まかに確認しておきます。
ここに、写真や図版を加えてレイアウトしたものが「校正紙」です。
「校正紙」を出しては校正して直し、出しては校正して直しを繰り返します。だんだんと細かい砥石で磨いていくようなイメージで、掲載内容の精度を上げていきます。
例えば、各回の校正では、誤字脱字のほか、こんなところをチェックします。
- 初校…大小の扱い、不足している素材など確認し修正
- 再校…初校の修正を見て、直すべきところの調整
- 三校…氏名などの固有名詞といった絶対に間違ってはいけない点のみ修正
というわけで「初校ででた修正希望なら直すけれど、三校では直さない」ということもでてきます。砥石のイメージを思い出していただけると、分かりやすいと思います。「最初からやり直し」なんですよね。
最近は章ごと、コーナーごとなど、数ページずつ校正紙を出してチェックすることも多くあります。そこで、誌面全体がそろったところで、さらに校正者による誌面全体を通した校正を行います。ここは、表記の統一やコーナーごとの記述の整合などを確認します。
複数人で校正するときのコツ
著者や発刊団体の担当者も校正紙のチェックをします。ここでは、誤字脱字のチェックというより、著者しかしらない事柄に間違いがないかや、発刊者の思いが反映されたものになっているかが主眼です。
気を付けたいのが、複数でチェックするときです。各々が好きに修正指示を思いつくままに出したら、なにがなんだか分からなくなります。
そこで、校正紙は以下のようにやりとりします。
- 校正紙をチェックする人全員が、編集方針や執筆ルールを理解してから校正する
- 全員が最新の校正紙を確認する
- 校正は然るべき人が目を通し、修正箇所はひとつの校正紙にまとめて記入する(主旨の異なる指摘が複数からあれば、編集会議で調整)
- 修正指示は五月雨式には出さす、ひとつのコーナーの分など、ある程度まとめて校正紙のやりとりをする
このあたりの調整も、編集者の大切なしごとです。
校正工程が錯綜したり煩雑になったりすると、発刊団体のみなさま、とくに担当者は大変な作業負担を強いられてしまいます。もちろん抜けや漏れにつながります。
記念誌や社史・家族史など、長く保管する冊子はとくに、誤字脱字などの間違いが許されません。100年、200年先まで胸を張れる冊子を作っていきましょう。
メルマガ登録はこちらから
ここだけに掲載している林原りかの「自分史的自己紹介」をお届け後、言葉やブランディングで、ビジネスと人生を充実させるヒントをお伝えしています。返信もOK!